
日本を代表する調味料である七味唐辛子。
実は、400年ほど前に誕生し今もなお、お蕎麦や丼ものにも使われている日本人に長く愛されてきた薬味の1つです。
しかし、改めて見ると「薬」という文字が入った調味料であり、薬と何か意味があるのかな?と気になるところ。
そこで今回は、七味唐辛子の歴史、薬と呼ばれる由来、日本三大都市をご紹介したいと思います。
日本人に愛される七味唐辛子の秘密に迫りたいと思います。
七味唐辛子は豊臣秀吉の時代にスタート?
七味唐辛子は、唐辛子を中心に複数のスパイスをブレンドして製造された調味料ですよね。その七味唐辛子の中心である唐辛子は実はコロンブスが大航海時代に船で世界を渡り歩いた時に唐辛子と出会い、ヨーロッパに持ち帰ったのが始まりとされています。
南米原産のものや、インドなどの香辛料が盛んな地域で栽培されており、次第に世界中に広まっていきました。日本に持ち込まれたのは、ポルトガルの宣教師が持ち込んだという説や豊臣秀吉が朝鮮出兵を行った際に持ち帰ったという説が幾つかありますが、おそらく1500年代に持ち込まれたと思われます。
そして、七味唐辛子として発売されたのは東京の今でいう両国あたりにある「薬研掘」で製造されたものが初となります。
なぜ七味唐辛子が薬と呼ばれているのか?
七味唐辛子を作った目的は漢方薬として用いられることを想定していたからと言われています。
中国では、けしの実や麻の実などはその高い栄養価から漢方薬としても使用されており、日本でも製造される際には風邪薬などの漢方薬として人に合わせて独自にブレンドして作られていたと言われています。
初代唐辛子は、東京やげん堀さんとなりますが、その後長野県の善光寺や京都の清水になる七味屋本家さんへと広がっていきました。
地域によって食文化が異なりますので、だし汁の濃い東では辛味の強い七味唐辛子がお好まれており、一方で京都の薄味文化で栄えた食文化では、あkらさよりも風味が重視されていました。
そのため、関西の七味唐辛子には、シソや山椒など風味に特徴のある薬味が選ばれており、今もなお多くの七味屋さんでこのような薬味が愛用されています。
また、七味唐辛子で使用されている薬味は、唐辛子、山椒、陳皮などが代表的。
唐辛子には、カプサイシンが含まれているので、発汗作用や血流を促進する働きがあるため、体の体温を温めてまさに風邪対策として体を冷やさないために配合されています。
他にも、山椒には風味成分が強くお出汁と相性が良く、陳皮にはビタミンCが豊富に含まれているので美肌効果や免疫力向上効果などが期待されています。ちなみに陳皮はみかんの皮を使用しており、お店によってはみかんの皮ではなく、ゆずの皮を使ったゆず七味というオリジナル商品を販売しているところもあります。
三大七味都市とはどこ?
先ほどもご紹介したように、七味唐辛子が発展した場所は「東京・長野・京都」が三大七味都市とされています。
観光に訪れた際には、ぜひこの3都市の味比べを行い自分好みの七味唐辛子巡りをしてみても面白いかもしれません。また、注目すべきはなぜこの3都市が七味唐辛子がもてはやされたのかということです。
実は共通があり、その3都市すべてに「お寺」が関係しているところです。
東京は浅草、長野県は善光寺、京都は清水界隈とどこもお寺がある場所となります。もともと漢方薬として作られていた代物ですが、一方で人によって好みの使用方法が生まれていきました。それは、一部の間でお坊さんが修行で冷えたからを温めることを目的に使用されていたとも言われています。
確かにカプサイシンの影響で体をポカポカと温めることができるので、冷えた体を温めるという目的でお坊さんから好まれたというのは一理ありそうです。
また、京都ではうどん文化に押されて七味唐辛子の相性が良いことや東京では蕎麦文化が背中を押して七味唐辛子が漢方薬という域を超えて調味料として好まれたというのも頷けるポイントとなります。
七味唐辛子は薬味が7種類とは限らない?
七味唐辛子は、名前から想像すると7種類の薬味が使用されていると思い込みがちですが、実はお店によって薬味の種類は異なります。
場所によっては8種類使っているところもありますし、唐辛子と焼き唐辛子を使用して8種類というお店もあります。
しかし、8種類使っていても、八味唐辛子とば呼びませんので予めご了承くださいませ。
最後に
いかがでしたか?七味唐辛子の普及には、意外と日本史につながりが深いことがお分かりいただけたかもしれません。
コロンブスの時代から今もなおつながりを持っていると知ると何か、これまでの七味唐辛子に対する見え方も少し変わってくるように感じますよね。
ぜひ、皆様も七味三大都市を訪れた際には、日本の食文化や普及の背景を感じながら旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。




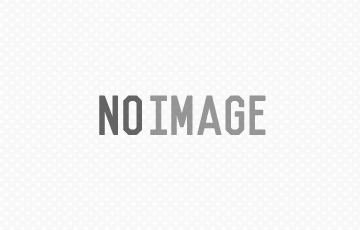

コメントを残す